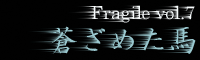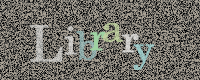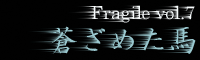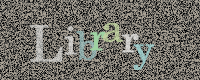|
<オウム真理教>による一連の事件にインスパイアされたと思われる映画「カリスマ」(監督 黒沢清)の中で、役所広司演じる刑事はこう問いかける。
「どちらも生き残る道はないのか?」と・・・。
この場合「どちらも」とは、カリスマと呼ばれる不思議な魅力をもった樹木(あるいはその樹木を信奉し守り続ける青年)と生態系を破壊するとの理由でその樹木を憎悪する大学教授や植林グループである。<オウム>に即して言えば教団(とその信者たち)と市民社会という構図になろう。あの事件から7年半余り経た今も、あちこちで教団の移住を巡るトラブルは絶えないと聞く。現実に倣うように物語はファナティックに展開しつつも、ついに両者が許し合うことはない。そんな情況に当初は中立的であった役所刑事も徐々に深入りし、狂気の淵を疾走しながらある覚醒を得てゆく。それは「生きることは殺すこと。殺すことは生きること。人間の生命としての摂理に委ねよ」というような意味のことだ。一見デンジャラスなメッセージだが、我々には馴染みの仏教的、禅的なポジティブなニヒリズムにも通じるだろうし、またビートルズならソフトに「Let it be」と歌うところだろう。映画は役所刑事がつかの間のドロップアウトを切り上げ、現実社会に還ってゆくことをほのめかして幕を下ろす。それを希望と呼ぶのは早計にしても後味は悪くない。
しかし二元論的悲劇を我々が未だ克服し得ていないのは、昨年9月11日の同時多発テロを見れば明らかであろう。どんな価値観も許容することを原則としたリベラリズムが、特定の価値観(例えばイスラム原理主義)を抑圧・疎外し、結果テロの標的にされたことは戯画的な皮肉でさえある。
「どちらも生き残る道はないのか?」・・・、痛切な問い掛けである。
本作「蒼ざめた馬」においても、残念ながら多くの人間が死ぬ。己の信条、帰属、血縁のために刺し違える。そのすべてが本意ならぬ死である。しかしせめて物語の中だけでも、累々たる屍の山の頂に希望の光が一筋でも射せばと願うのだが・・・、まぁ、そんな甘くはあるまい。
本日はご来場いただき誠にありがとうございます。無名の劇作家と演出家の愚鈍な冒険にどうかお付き合いください。
俳優座版「蒼ざめた馬」パンフ寄稿
(文責 小里 清)
|